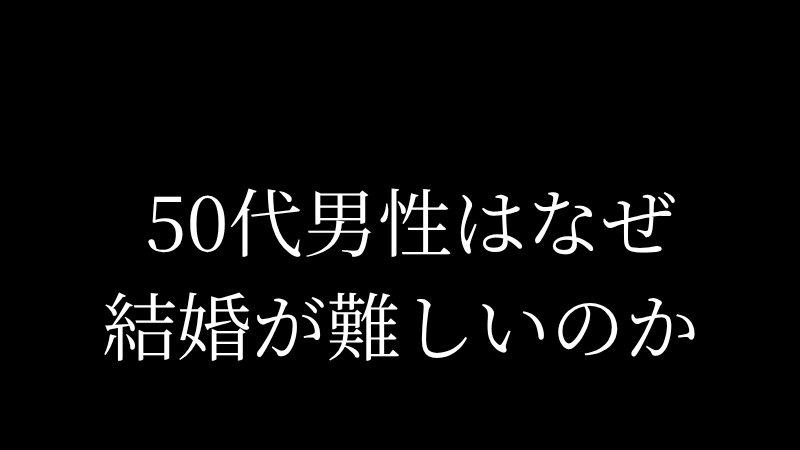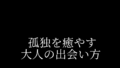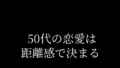なぜ、結婚したい希望を持つ男女が、これほど結婚できなくなったのでしょうか?
この問いは、もはや「個人の努力」「恋愛経験の多寡」といった要因では説明できなくなっています。
総務省、厚生労働省、社会保障・人口問題研究所(社人研)が公表する統計を横断すると、未婚化の背景には
- 雇用と所得の二極化
- 地域間人口移動の偏り
- 家族観の変化
- 恋愛機会の減少
など、社会構造の変化が複雑に絡み合っていることが見えてきます。
東洋経済オンラインの専門家対談が示した問題意識を起点にしつつ、本記事では 個人の努力では突破できない壁の正体 を丁寧に解説します。
📚 参考元記事
出典:東洋経済オンライン
「社会構造的に『結婚できない男女』がいる大問題」
(山田昌弘 植草美幸、2019年8月公開)
👉 記事を読む
※本記事は上記内容に着想を得て再構成したものであり、
公的統計・実データをもとに「50代男性はなぜ結婚が難しいのか?」の構造的理由を解説しています。

50代男性が結婚できない本当の理由 データで読む社会構造
50代男性が結婚しづらいのは、本人の努力や性格の問題ではありません。未婚率の上昇、家族観の変化、雇用の不安定化など、複数の社会構造が重なってハードルを上げています。まずはこの見えにくい障壁を整理します。

日本の未婚率は個人の問題ではなく構造問題
日本の未婚率の上昇は、恋愛や努力の不足といった個人の要因だけでは説明できない段階に入っています。総務省『国勢調査』によると、50歳時点で未婚のままの男性は28.3%に達しています。1990年にはわずか5.6%だったことを考えると、驚くほど急激な上昇といえます。
この背景には、所得の伸び悩み、非正規雇用の拡大、若年層の都市集中、家族観の多様化など、社会全体の構造変化が積み重なっていると考えられます。恋愛や結婚は本人のやる気だけで決まるものではなく、環境条件に大きく左右されます。そのため、条件が整わない限り、個人が努力しても成果が出にくい状況になっています。
東洋経済オンラインの対談でも指摘されているように、偶然の出会いが減り、相談所やマッチングアプリに頼らざるを得ない時代になりました。しかし、これらの市場でも、女性側が求める条件に合う男性が少なく、結果として判断基準が厳しくなり、未婚化がさらに進む要因となっています。
このように、未婚化はもはや個人の問題ではなく、社会構造が生み出している問題だといえます。
所得・雇用の非対称性が結婚市場の入口を狭くした
日本の結婚市場の機能不全を後押しした最大の要因は、雇用・所得の二極化だといえます。厚労省や国税庁のデータを見ると、30〜40代男性の所得中央値は350万円前後で推移しており、1990年代後半のピークから大きく低下しています。一方で、女性が結婚相手に求める最低年収は400〜500万円台が長年の主流で、ここ30年間ほとんど変化していません。
つまり、「女性が求める年収ライン」は固定されたまま、「男性の所得だけが落ち続けてきた」のです。この非対称性が、婚活市場に恒常的なミスマッチを生み出しています。条件を満たす男性は争奪戦になり、中央値層の男性はスタートラインに立つ前に脱落しやすい構造になっています。
また、相談所の入会基準も年収ラインで男性をふるいにかけるため、所得が低い男性ほど参戦すらできない状態に置かれます。努力や恋愛スキルの問題以前に、市場そのものが入口を閉じているというのが現実なのです。
恋愛経験が格差化し、そのまま結婚格差へ転化している
恋愛は経験値が蓄積される領域であり、若い頃に恋愛経験が少ない男性ほど、年齢を重ねるほど不利になっていきます。社人研の調査でも、「交際経験がないまま30代後半に突入する男性」が過去最高を記録しており、恋愛の未経験組が確実に増えています。
これは単なるモテ・非モテの問題ではなく、恋愛の基礎スキル—適切な距離の取り方、会話の温度調整、相手の心理を読む力—を学ぶ機会そのものが減っていることを意味します。さらに、SNSの普及によって「断られるリスクを避けたい」というリスク回避思考が若年層ほど強まり、最初の一歩を踏み出せないまま年齢だけが進むケースが増えています。
その結果、恋愛経験の差がそのまま結婚可能性の差として固定化し、婚活の現場では「会話が続かない男性」と「経験豊富な女性」とのギャップが顕在化しています。恋愛格差が結婚格差へ転化していることこそ、現代日本の大きな構造的特徴だといえます。
年収と雇用形態が50代の婚活を難しくする 結婚市場の現実
婚活市場に最も大きく影響を与えているのが、所得と雇用の二極化です。年収別の需給ギャップは50代ほど顕著で、努力では埋まらない構造的な壁になっています。データから、その歪みの正体を読み解きます。

年収分布の現実が「結婚市場の需給バランス」を根底から崩している
日本の結婚市場で起きている根本的な問題は、男女の希望条件と現実の年収分布が全く噛み合っていない点にあります。男性の年収ボリュームゾーンは300〜399万円台で、中央値は350万円前後にとどまっています。一方、女性が結婚相手に求める最低年収は、複数の調査で長年「400万円以上」が最多で、5〜7割がこのラインを希望しています。
つまり、市場には女性が求める男性層がそもそも十分に存在していないのです。この需給ギャップは、女性の要求が高いというよりも、男性の所得構造が長期的に低下してきたことの結果だといえます。
結婚相談所でも「条件に合う男性は極端に少ない」と指摘されており、現場感覚と統計が完全に一致しています。需給が釣り合っていない市場では、一部の上位男性に人気が集中し、中央値の男性が排除されやすい構造が生まれます。
つまり、婚活がうまくいかない理由は本人の問題ではなく、そもそも分布の問題なのです。
女性の希望年収ラインは30年ほぼ不変、男性の所得だけが下がり続けてきた
1990年代から2020年代まで、女性が結婚相手に求める最低年収は400〜500万円台でほぼ横ばいで推移しています。経済環境が悪化しても、この希望ラインは下がっていません。一方で、男性の所得中央値は長期停滞が続き、ピークだった1997年を境に右肩下がりとなり、現在の30〜40代では350万円前後まで低下しています。
この30年間で起きたことは、「女性の要求が高くなった」わけではなく、「男性の所得だけが落ちた」という一方的な変化です。希望条件と実態の差が年々開き、結婚市場の不均衡は固定化されつつあります。東洋経済オンラインの対談で「年収の線引きで男性が大量に脱落する」と語られていたのも、この構造を正確に反映しています。
女性は過去の成功体験や周囲の結婚像を基準に条件を決めるため、年収ラインを簡単に下げることができません。希望条件が動かない限り、所得構造の変動はそのまま未婚化の加速要因になっていきます。
非正規雇用の拡大が結婚できない男性層を構造的に増やした
日本の未婚化を押し上げた重要な要因が「非正規雇用の拡大」です。総務省『労働力調査』では、男性の非正規比率は1990年代後半から急増し、現在の未婚男性では約3割が非正規に属しています。非正規の平均年収は正規の6割程度にとどまり、賞与や昇給が乏しいため、長期的な生活設計が難しくなります。
厚労省のデータによると、非正規男性の既婚率は正規の3分の1以下にまで落ち込み、年収300万円未満層の未婚率は突出して高いという結果が出ています。つまり、「所得が低いから結婚できない」のではなく、「非正規雇用という構造が、結婚可能性そのものを奪っている」ということです。
結婚相談所の入会基準でも非正規は不利になりやすく、多くの男性が婚活のスタートラインに立つことすらできない状況に置かれています。雇用構造が恋愛や結婚の運命を左右している現実は、個人の努力だけでは覆せないレベルに達しているといえます。
恋愛経験ゼロが50代の婚活に与える影響 経験格差の正体
若い頃の恋愛経験がその後の恋愛力を決定づける─これは婚活研究でも示されている傾向です。しかし50代男性の多くは、仕事最優先の生活で恋愛機会が乏しく、その蓄積差が今の壁となっています。恋愛経験の非対称性を整理します。

恋愛経験の格差が結婚可能性の格差へ転化している
現代日本では、恋愛経験そのものが格差として固定化し、結婚可能性の差へと直結しています。社人研や内閣府の調査でも、10〜20代で交際経験がなかった男性ほど、30代以降も恋愛に消極的になりやすく、そのまま未婚に至る確率が高いことが示されています。
理由は明確で、恋愛は経験を通じてスキルが蓄積される領域だからです。適切な距離の取り方、温度を合わせる会話、相手の緊張をほどく姿勢、これらは実践によってしか身につきません。
一方、女性側は若い頃から恋愛経験が比較的豊富なケースが多く、経験値の非対称性が婚活の場で顕在化します。「会話が噛み合わない」「温度差がある」といったミスマッチは、性格の問題ではなく経験格差が表面化した結果です。
経験値を持つ側と持たない側、その差がそのまま結婚確率の差として再生産される社会構造ができ上がっているのです。
偶然の出会いが消滅し、恋愛が自己責任化した結果、格差が固定化した
かつて日本には、職場・学校・地域・友人の紹介といった偶然の出会いが豊富に存在していました。総務省『社会生活基本調査』を見ても、1990〜2010年代の間に「対面コミュニケーション総量」が大幅に減少し、特に若者の異性接触は半分以下に落ち込んでいます。
偶然の出会いが消えれば、恋愛機会は自分で作るしかない状態になりますが、日本では積極的に声をかける文化が強くありません。東洋経済の対談でも「偶然の恋愛ルートはほぼ消滅した」と指摘されていたように、恋愛が完全に自己責任化した社会では、外向性の高い人・都市部在住者・異性の多い職場にいる人だけが恋愛経験を積み重ねます。
逆に、そうした環境にいない人は、経験ゼロのまま年齢だけが進みがちです。環境差がそのまま恋愛差となり、恋愛差が結婚差として固定されていきます。偶然の消滅が、静かに恋愛格差を拡大し続けているのです。
スクールカースト的なモテ階層が大人になっても固定され続ける日本社会
日本では、学生時代のモテ階層が成人後も再生産されるという特殊な構造があります。内閣府の若者調査によると、高校時代に恋愛経験があった男性は、その後の結婚率が圧倒的に高くなります。一方で、10代で交際経験のなかった男性は、30代・40代になっても恋愛機会を得にくく、そのまま未婚へ向かいやすい傾向があります。
その背景には、情報格差、友人関係の偏り、異性との接触の機会差が累積し、恋愛スキルの獲得に初期ハンディキャップがついてしまうことがあります。東洋経済の対談でも「モテる男性はモテる男性同士でつながり、非モテ層は同じ層で固まる」と語られていましたが、この現象は統計データとも一致しています。
環境によって異性との接触機会が階層化されている日本では、こうしたカースト的構造が更新されにくく、恋愛・結婚の両方で差を生み続けます。若い頃のスタート位置がその後の人生を左右してしまうという、非常に残酷な構造が存在しているのです。
女性側の事情 家事負担と恋愛経験が結婚に結びつかない理由
女性の恋愛経験は多いのに、なぜ結婚にはつながらないのか─背景には恋愛経験の非連続性と家事負担の過大さという構造問題がある。ここでは女性側の結婚困難の実態を整理します。
女性の恋愛経験は多いのに結婚に結びつかない 恋愛経験の非連続性という問題
女性は若い頃の恋愛経験が比較的豊富ですが、その経験がそのまま結婚成功へ移行しにくいという非連続性が生まれています。ブライダル総研や社人研の調査でも、20〜30代前半の女性は高い交際率を示す一方で、「結婚に発展しない恋愛」が増えていることが確認されています。
その背景には、20代の恋愛が楽しむことを中心にしており、結婚を前提とした関係でないケースが多いという事情があります。相手に結婚意欲がないまま長期間交際し、気づけば婚期を逃す例も少なくありません。東洋経済の対談でも「恋愛経験が豊富な女性ほど、なぜ結婚に至らないのか分からず悩む」という指摘がありました。
恋愛経験がいくら多くても、結婚を成立させるために必要な交渉力・生活設計・相手の人生観の見極めといったスキルは別物です。恋愛の量が、結婚の質や婚期に直結しない点こそ、現代日本のはっきりとした特徴だといえます。
家事・育児負担の固定化が女性にとって結婚のコストを過大化させている
女性が結婚に慎重になる最大の構造要因のひとつが、家事・育児負担の不平等です。厚労省や内閣府の男女共同参画調査では、共働き家庭であっても家事・育児の7割以上を女性が担っていることが示されています。これは結婚=負担増という実感を女性に与え、婚活の判断基準を厳しくする大きな要因になります。
たとえ恋愛関係が順調でも、「結婚したら自分ばかりが家事を背負うのではないか」という不安が強く、相手選びに慎重にならざるを得ません。その結果、男性に求める条件が厳格化する傾向が強まります。また、出産によるキャリア中断や収入低下のリスクも女性側に偏っており、結婚が経済的マイナスとして認識されるケースも少なくありません。
東洋経済の対談で「家事ができる男性は刺さる」と語られていたのは、裏を返せば家事をしない男性が依然として多数派であるという現実の反映です。結婚は女性にとって今なお高コストであり、それが結婚の遅れや未婚化の一因となっています。
50代男性の婚活を阻む「親の価値観」 昭和型家族の呪縛
「こうあるべき」という家族像や、親世代の価値観が50代の婚活を縛ることがあります。本人の希望ではなく周囲の期待が結婚の判断を難しくしてしまう、見えにくい心理的ハードルを整理します。
親の価値観がそのまま結婚の妨げになるパラサイト世帯の深刻化
日本の未婚化には、「親世代の価値観が結婚を妨げている」という、海外ではあまり見られない独特の構造問題が存在します。東洋経済の対談でも紹介されていたように、50代男性の婚活には80代の母親の影響力が強く、「家事ができる女性でないとダメ」「親と同居すべき」といった昭和的価値観を押し付けられ、交際が順調でも親の反対で破談になるケースが少なくありません。
総務省『就業構造基本調査』でも、成人後も親と同居するパラサイト世帯が増え続けており、その生活習慣や依存構造が子どもの恋愛判断にまで影響を及ぼしていることが示唆されています。親が苦労させたくないと保護を強めるほど、自立は遅れ、生活能力や決断力が十分に育たないまま50代に突入する人も増えています。
その結果、恋愛が始まっても親の反対という外的要因が結婚の壁となり、未婚のまま終わってしまう例が後を絶ちません。未婚化は若者だけの問題ではなく、三世代構造の固定化が生み出す、日本固有の社会問題でもあるのです。
地方50代男性が結婚できない地理的理由 都市集中と出会い格差
都市と地方では、出会いの母数・年齢構成・移動距離がまったく異なります。特に地方では若い女性の流出が続き、50代男性には圧倒的に不利な状況です。地理が婚活に与える影響を整理します。
都市部と地方で出会いの構造が完全に分断されてしまった
日本の未婚化を語るうえで見逃せないのが、地理的構造による格差です。総務省『住民基本台帳人口移動報告』を見ると、20代女性の大都市圏への流入は依然として続いており、地方の若い女性人口は急速に減少しています。東洋経済の対談で「うどん屋に独身女性が集中する」という描写があったのは、この都市集積の現実を象徴しています。
一方で、地方では若い女性そのものが少なく、職場・地域・コミュニティの人間関係も固定されやすいため、偶然の出会いはほとんど発生しません。さらに、車社会で行動範囲が限定され、噂が広まりやすい環境は、ナンパや自由な恋愛を難しくします。
その結果、都市は出会いが多い世界、地方は出会いがほぼない世界として完全に二分化し、恋愛機会そのものが地域によって決定される構造ができあがっています。恋愛を個人の努力でどうにかできるとみなす議論は、この地理的前提を見落としているといえます。
日本の結婚制度が50代に不利な理由 制度と現実のズレ
日本社会は依然として結婚前提の社会設計を続けています。しかし現実には、結婚しやすい条件が急速に失われています。この二重の矛盾が50代の婚活を困難にします。
制度は結婚前提のまま、現実は結婚しにくい方向へ進む日本的ジレンマ
現代日本は、「結婚しないと生きにくい社会」でありながら、「結婚できる前提条件」が静かに消えていくという矛盾を抱えています。税制・社会保障・住宅ローン・介護制度など、ほぼすべてが「夫婦単位」「家族単位」を前提に設計されているため、独身者は制度のすき間に落ちやすくなっています。
一方で現実は、所得の低下、雇用の不安定化、若い女性の都市集中、偶然の恋愛機会の消滅といった要因が重なり、結婚しやすい条件が急速に剝がれ落ちています。東洋経済の対談でも「いまの制度は結婚ありきで作られているが、結婚に至るルートはどんどん細くなっている」と指摘されていたように、日本は「制度は昭和のまま、現実だけ令和」という時間差構造を抱えたまま立ち止まっているのです。
その結果、50代男性は「制度の圧力」と「現実の困難」の両方を背負わされる形になり、婚活の難易度はさらに上がっていきます。
50代の婚活は「再設計」が鍵 距離感・余白・会話の方法
50代の出会いは、20代の「恋愛の再演」ではありません。
むしろ、人生の後半をどう生きるかという「再設計」に近いものです。
孤独の抱え方、会話のリズム、距離感の取り方──若い頃とはまったく異なる技法が必要になります。
ここでは、50代が現実的に出会いを進めるための心理技法と設計思想を、丁寧に掘り下げていきます。
50代は何を手放し、何を残すかを決めるフェーズに入る
50代の出会いでは、若い頃のような「全部盛りの恋愛」は成立しません。
むしろ、何を手放し、何を残すかという取捨選択が中心になります。
仕事・家族・健康・資産・趣味─背負ってきた荷物が多い年代ほど、相手に求める条件は複雑化しがちですが、本当に必要なのは「生活の相性」「リズムの一致」「沈黙が苦にならない関係」といった実存的な要素です。
20代のように「ときめき」中心で選ぶわけではなく、50代では「生活の共同運転が可能かどうか」が判断基準になります。東洋経済の対談でも「50代は条件より生き方の相性が重要」と語られていました。
逆に言えば、生き方を再設計しないまま婚活に踏み込むと、20代の成功体験に縛られ、選択軸がズレて苦戦しやすくなります。
まずは、自分の「心の余白」をどこに作るのかを決めることが、50代の恋愛の出発点になるのです。
距離の最適化が若い頃より10倍重要になる
50代が恋愛でつまずきやすい理由のひとつが、「距離感のチューニング」です。若い頃は勢いで距離を縮めても関係が破綻しにくいものですが、50代になると相手も人生経験が長く、明確な境界線を持っています。
仕事・家族・過去の恋愛・個人の価値観─これらがすでに固まっているため、「踏み込み過ぎ」は即アウト、しかし「距離を空け過ぎる」と関係が停滞します。この絶妙な距離を最適化するためには、観察力と余裕が欠かせません。
東洋経済の対談でも「50代は相手の生活ペースを尊重できる人が強い」と強調されていました。LINEの頻度、デートの間隔、会話の深度──どれも50代では「過不足」が相手に敏感に伝わります。
若い頃のように勢いに任せず、「中庸の距離」を調整できるかどうかが、50代の恋愛成功率を大きく左右するのです。
人生のメタ認知が恋愛力を決定づける年代に入る
50代の出会いで最も重要なのは、「自分の人生を一段高い視点から見直すメタ認知力」です。若い頃の恋愛は、感情の勢いだけでも何とかなる部分があります。しかし50代では、生活基盤・健康・将来設計・老後の不安など、複数の現実が絡むため、恋愛の判断には自己理解の深さが欠かせません。
「自分はどんな関係を求めているのか」「何を恐れているのか」「どこにズレが生まれやすいのか」を冷静に観察できるほど、相手とのコミュニケーションは安定し、関係も長続きしやすくなります。東洋経済の対談でも、「メタ認知の欠如が婚活を失敗させる最大要因だ」と指摘されていました。
50代の恋愛は、自分をアップデートする工程でもあります。だからこそ深みがあり、味わいがあります。人生の折り返し地点に立つからこそ、恋愛が第二のスタートラインになるのです。
50代の婚活は構造を読み解かなければ勝てない【まとめ】
50代が婚活で苦戦するのは、性格や努力ではなく構造の問題です。所得の二極化、非正規雇用の拡大、若い女性の都市集中、恋愛機会の減少、経験格差の固定化、親世代の価値観の干渉─これらはすべて個人の力では動かせない外部環境です。
だからこそ重要になるのは、構造の中でどの戦略を選ぶかという視点です。若い頃の恋愛を再演しようとすれば必ず行き詰まりますが、50代なりの距離、余白、生活リズムを基準に再設計すれば、むしろ最も安定した関係を築きやすい年代でもあります。
構造を理解し、その中で現実的な技法を選び取ること─それこそが50代の婚活の核心であり、戦略なのです。
50代の出会いを「構造戦略」から実践に落とす
構造の話だけ聞いても、「自分はどこで、どう動けばいいのか」が一番気になるところだと思います。
50代の婚活は、若い頃のように勢いで動けばうまくいく時代ではありませんが、
「場の選び方」と「距離感の取り方」を変えるだけで、現実はかなり動きます。
この記事の後編では、次のようなポイントを具体的にまとめています。
- 50代男性が「無理をせずに」出会いを増やす場の選び方
- 距離感をこじらせないためのメッセージ・会話のコツ
- 結婚にこだわりすぎず、「まずは安心して会える相手」を見つける実践ステップ
【後編】50代男性のための「現実的な婚活・恋愛の技法」はこちら
なお、実際に「大人同士の落ち着いた出会い」を試してみたい方には、
30歳以上限定のコミュニティである 華の会メール をおすすめします。
登録は無料、試してみて合わなければすぐにやめることも可能です。
「とりあえず、今の自分の条件でも相手はいるのか?」を静かに確かめてみるくらいの感覚で十分です。
この記事の続き(実践編)はこちら
構造を踏まえたうえで、50代男性が実際にどんな技法で動けばいいのかを解説しています。
→ 【後編】50代男性が結婚できない本当の理由と現実的な解決策【実践編】
出典・参考資料
- 東洋経済オンライン『社会構造的に結婚できない男女がいる大問題』(2019年8月掲載)
- 総務省『国勢調査』
- 総務省『労働力調査』『社会生活基本調査』『住民基本台帳人口移動報告』『就業構造基本調査』
- 厚生労働省 各種統計・男女共同参画調査
- 国税庁『民間給与実態統計調査』
- 社会保障・人口問題研究所(社人研)『出生動向基本調査調査』
- リクルート ブライダル総研『恋愛・結婚調査』
- 内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』